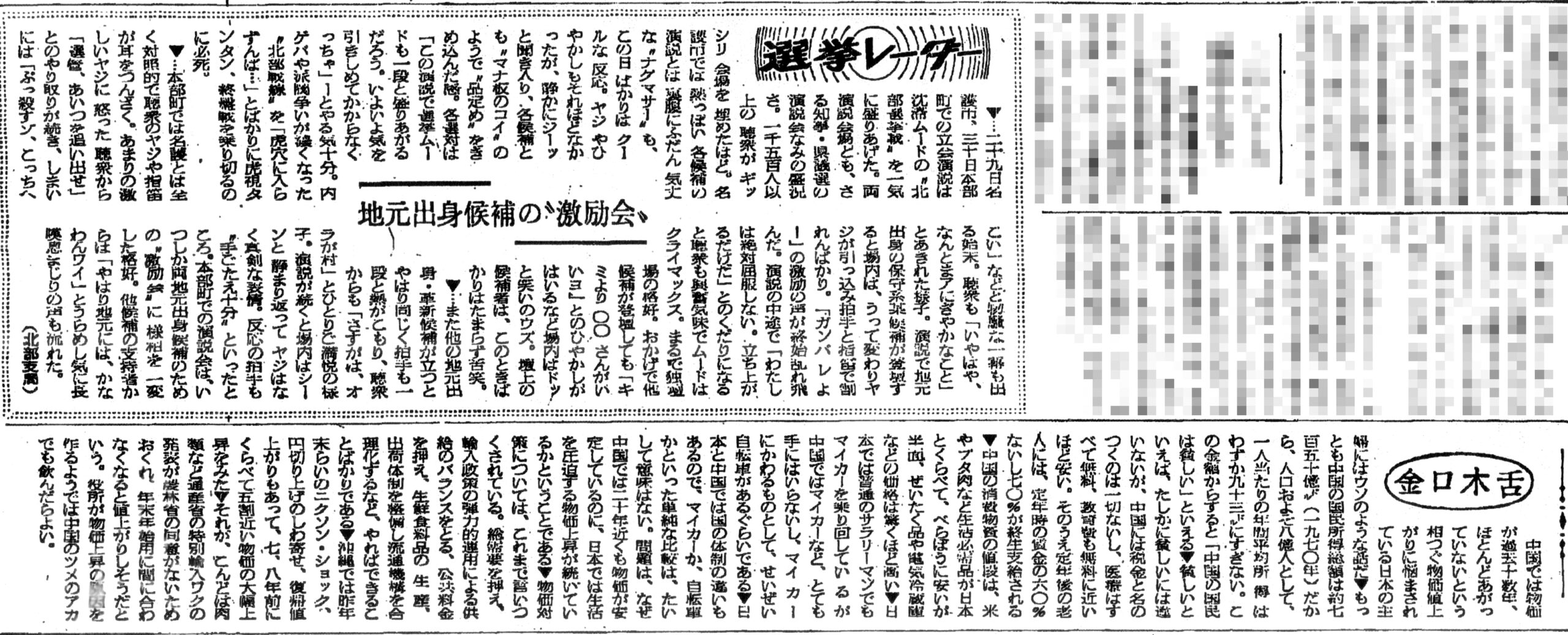ここ数日、ブログ主は溜まりにたまった新聞史料のデジタル保存に取り組んでますが、その過程で興味深い記事を見つけました。数日前に、何か日中間でもめ事があったようですが、今回紹介する記事は復帰直後の我が沖縄の意識高い人たちの “ちうごく感” を伺う面白い内容になっています。
その前に復帰前後の社会状況を補足しておくと、当時の沖縄は前年度のニクソン・ショック(ドル切り下げ)の影響で、生活必需品を含む物価が大幅な値上げ状態にありました。プラス、アメリカ世時代の米国民政府は直接税重視(すなわち間接税軽視)の税制だったので、社会全体に “重税感” が漂っていたのです。
その点を踏まえて昭和47年12月2日付琉球新報〈金口木舌〉を読むと、日本のお役人さんの無策ぶりを嘆く気持ちと、お隣の中国共産党の政治がうらやましいと思うのも理解できます。たしかに過去数十年物価が上がってなかったかもしれませんが、文化大革命当時、
人命の価格のデフレ傾向が鮮明だった
中国大陸の “ツメのアカは飲みたくない” と余計な突っ込みを入れたブログ主であります。全文を紹介しますので、是非ご参照ください。
中国では物価が過去数十年、ほとんどあがっていないという。相つぐ物価値上がりに悩まされている日本の主婦にはウソのような話だ。
▶もっとも中国の国民所得総額は約七百五十億㌦(一九七〇年)だから、人口およそ八億人として、一人当たりの年間平均所得はわずか九十三㌦にすぎない。この金額からすると「中国の国民は貧しい」といえる。
▶貧しいといえば、たしかに貧しいには違いないが、中国には税金と名のつくのは一切ないし、医療はすべて無料、そのうえ定年後の老人には、定年時の賃金の六〇%ないし七〇%が終生支給される。
▶中国の消費物価の値段は、米やブタ肉など生活必需品が日本とくらべて、べらぼうに安いが半面、ぜいたく品や電気冷蔵庫などの価格は驚くほど高い。
▶日本では普通のサラリーマンでもマイカーを乗り回しているが中国ではマイカーなど、とても手にはいらないし、マイカーにかわるものとして、せいぜい自転車があるぐらいである。
▶日本と中国では国の体制の違いもあるので、マイカーか、自転車かといった単純な比較は、たいして意味はない。問題は、なぜ中国では二十年近くも物価が安定しているのに、日本では生活を圧迫する物価上昇が続いているかということである。
▶物価対策については、これまで言いつくされている。総需要を押え、輸入政策の弾力的運用による供給のバランスをとる、公共料金を押え、生鮮食料品の生産、出荷体制を整備し流通機構を合理化するなど、やればできることばかりである。
▶沖縄では昨年末らいのニクソン・ショック、円の切り上げのしわ寄せ、復帰値上がりもあって、七、八年前にくらべて五割近い物価の大幅上昇をみた。
▶それが、今度は肉類など通産省の特別輸入ワクの発表が農林省の同意がないためおくれ、年末年始用に間に合わなくなると値上がりしそうだという。役所が物価上昇の原因を作るようでは中国のツメのアカでも飲んだらよい。(昭和47年12月2日付琉球新報朝刊1面)