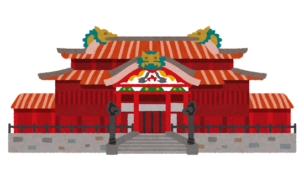
普天間基地の名護市辺野古移設に関わる、大浦湾側の地盤改良工事の設計変更申請を「承認」するよう国が県に求めた「指示」に絡んで、前回の記事の中で(結果として)玉城知事が二度も “民主主義の失敗” に関わった政治家である件に言及しました。今回は「現時点(5日)では承認とも不承認とも確定できないとして、判断できないと回答した」との、いわゆる「判断困難」について考察します。
この案件について、関連記事をチェックした上で確信できたのは、9月上旬の時点で知事サイドには「不承認を宣言」する選択はなかった件です。理由は最高裁判断に対して正面から異を唱える県政上のリスクは無視できない訳であり、それを踏まえて「承認」か「判断示さず」の2択に絞られていたのは間違いありません。
そして、誤解を恐れずにハッキリ言うと、玉城知事の本音は 「承認」です。もちろん行政の長として当然の判断であり、新聞報道によると県庁内ではその方向で進んでいたのですが、最後に「民意」によってひっくり返された形になりました。
参考までに、当ブログ「辺野古訴訟 県敗訴の考察」の中でブログ主は以下のように言及しました。
ちなみに一番最悪なパターンは、「判決を受け入れ、地盤改良工事を認めた場合」に想定される身内から「公約違反」の誹りを恐れて、判断を先延ばしにすることで国が代執行手続きに入ることです。その場合は「最高裁の判断に従わない県知事」のレッテルが貼られることになり、一部の支持者を除いて、世間からごうごうたる非難を浴びること間違いないでしょう。(下略)
今回の知事の態度の何が最悪かと言うと、今更ながらですが、沖縄県知事は大事な場面で断固たる決断ができない政治家であることを証明した点です。いわば、
政治家としての賞味期限が切れました
と日本中にアピールした形になったわけですが、「承認」した後の “支持者の暴走” を知事サイドが恐れた結果であることは疑いの余地ありません。
たしかにオール沖縄を構成するコアメンバー、そしてそれを取り巻く支持者を見ると、玉城知事の懸念は痛いほど理解できます。つまり知事を支えると公言している支持者たちの存在が、結果として彼の政治家としての “決断力” を発揮できない状況を作り上げているのであり、それはまさに明治9年(1875)の尚泰王を取り巻く状況と同じなのです。
参考までに当時の状況を大まかに説明すると、明治5年(1872)年9月の琉球藩の設置(明治天皇より琉球藩王に封ぜられる)、その後の征台の役(1874年)を経て、明治9年(1875)7月、来琉した松田道之(当時の肩書は内務大丞)よりもたらされた明治政府の「達書」を遵奉するか否かで琉球藩内は大騒ぎになります。
『尚泰王実録』によると、同年9月に藩王は「遵奉」を決意し、那覇に滞在していた松田宛に遵奉書を携えた正使を派遣しますが、首里城および那覇(実録によると久米)で大騒動が起き、使者は首里城に引き返さざるを得ませんでした。事態を重く見た松田の取り計らいで、琉球藩の全権委任大使を東京に派遣し、そこで「遵奉」する手はずになったのですが、今度は池城親方をはじめ琉球藩の大使たちが約束を「反故※」にしてしまい、結果的に尚泰王は決断のタイミングを逸してしまったのです。
※この件は明らかな「王命違反案件」なのですが、明治政府に対して二枚舌を使った使者たちはなぜか不問に処されます。そしてこの時の大失態により、琉球藩は「遵奉」も「拒否」もしない、ひたすら現状維持を訴え続ける交渉しかできなくなり、明治政府からの信頼を失ってしまったのです。
政治家には現状を変えるために決断力を発揮せざるを得ない “時” がありますが、尚泰王も玉城知事も身内のよって決断できない状況に追い込まれてしまいました。明治のケースは「清国の恩義」、そして令和の今日は「民意」が大義名分になっているのですが、その根底にあるのは臣下(あるいは支持者)の
是迄通(これまでどおり)でありたい
との強烈な現状維持願望であるのは疑いの余地ありません。特にオール沖縄は県が「承認」した時点で結束崩壊間違いなしの状態になるため、必死になって玉城知事にプレッシャーをかけたのです。
ただし、尚泰王と玉城知事との違いについても言及しておくと、明治9年当時の尚泰王は精神を患っていて首里城に引きこもり状態になっていたのに対し、現代の玉城知事は健康体そのものあることと、代執行訴訟の結果次第で「承認」する余地が残されている件です。
尚泰王の場合は明治9年の不決断が結果として王家を滅亡に導きました。やはり政治家が決断できないリスクは “計り知れない” というのが歴史の教訓であり、それを踏まえて玉城知事にも後世のために “断固たる決断” を僅かながら期待しつつ、今回の記事をまとめた次第であります。(終わり)