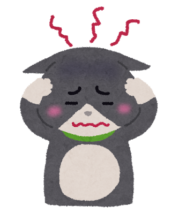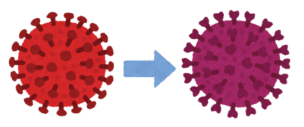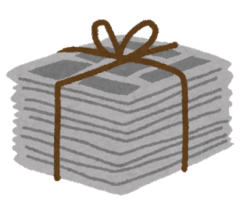今月31日に投開票が行われる国政選挙(第49回衆議院議員選挙)に関して、現時点でブログ主が気が付いた異変について言及します。というかブログ主は選挙ウォッチャーでもガチ勢でもないため、各地区の勝敗予想については詳しく説明できませんが、それでも前回の国政選挙との大きな違いに気が付きました。
翁長雄志氏の偉大さを痛感したお話。
今月4日、那覇市内を散策中のブログ主は、ふと気になった光景を目にしましたので写真撮影してきました。ご存じのとおり今月14日に衆議院が解散され、19日に公示、31日に投開票が行われる日程がきまり、立候補が噂される政治家たちが各地で事務所を開いたり、街頭活動に従事する姿を見かけるようになりました。
うちなーのすき焼き
今回は当ブログで意外に取り上げたことがなかった “うちなーのすき焼き” を紹介します。よくよく考えてみると、定食屋ですき焼きを注文すること自体あまりなかったのですが、数日前に “沖縄のすき焼きは何か違う” との題字のWEBサイトを閲覧して、興味を持ったブログ主は、さっそくですが那覇市松山の “お食事処 三笠” を訪れてみました。
修羅の邦りうきう – 昭和の三面記事より
ご存じの読者もいらっしゃるかと思われますが、10月1日に緊急事態宣言が解除されたことに伴い、沖縄県立図書館の入館が再開され、ブログ主は早速ですが新ネタを入手するために図書館を訪ねてきました。
今回は本来であれば “修羅の邦りうきう – コザその1” の続編を予定していましたが、ブログ主の予想の斜め上を行くじわじわくるネタを仕入れてきましたので先に紹介します。3面記事好きの読者のみなさん、是非ご参照ください。
ユタとりうきう その2
前回はユタとりうきうと題してブログ主なりにユタについて言及しました。既出ですが我が琉球・沖縄の歴史においてユタの存在を歴史的に解明し、その解決策を明示したのは伊波普猷先生が最初です。
大正2年(1913)3月11日から琉球新報に掲載された「ユタの歴史的研究」の〆の部分で、伊波先生はユタ対策について以下のように言及されております。
“ぼくのかんがえるさいきょうの” という病
今回は我が沖縄だけでなく、日本全国(特にネット上)ではびこる “ぼくのかんがえるさいきょう” の弊害について言及します。ちょっと意地悪な内容にはなりますが、その好例として沖縄県内における中国観の変遷について簡単に説明します。
修羅の邦りうきう – コザその1
昨今の新型コロナウィルス感染症対策に絡んで沖縄県立図書館が休館中のため、残念ながら新ネタをゲットできないブログ主は、暇つぶしにこれまで蒐集した新聞記事を再チェックしたところ、予想通り素でエグい内容の記事を多数発見しました。
ユタとりうきう
少し前に当ブログで “りうきうにおける神権政治” についての記事をアップしましたが、今回はそのついでにりうきう社会におけるユタについて言及します。
その前にブログ主なりにユタを定義すると、大雑把には “民間から自然発生した神に操られる者たち” で、この点が重要ですが彼ら(あるいは彼女らは)琉球王国時代の神女組織とは(原則として)独立した存在だったのです。参考までにりうきう社会の神女組織について、伊波普猷著『ユタの歴史的研究』を参考にまとめてみると、
金秀グループのオール沖縄離脱に関連して、突っ込まざるを得ない記事をピックアップした件。
既報でご存じの読者も多いかと思われますが、今月15日付沖縄タイムス1面に “金秀「オール沖縄」推さず” の題字で金秀グループの呉屋会長が、オール沖縄に対しこれまでのようにグループとして支持や支援は行わない旨の記事が掲載されていました。
ポーク玉子おにぎりを食べ歩いたお話
今回はちょっと趣向を変えて “ポーク玉子おにぎり” の食べ歩きレポをアップします。平成の世にポーク玉子おにぎりが登場して以来、もはや県民食として認知された感がありますが、それに伴い那覇市の国際通りには観光客目当ての専門店がオープンしています。
【補足】りうきうにおける神権政治とは
前回アップした “【島津入り】りうきうはなぜ薩摩に敗れたのかの考察 “がブログ主の予想の斜め上を行く反響を呼んだので、今回は理解の補足資料として神権政治(シオクラシー)について言及します。
ちなみに現代のうちなーんちゅは日常生活において “神” を意識する機会がほとんどありませんが、古りうきう民の神概念を考察すると、大雑把ではありますが下図のようにまとめることができます。
【島津入り】りうきうはなぜ薩摩に敗れたのかの考察
当ブログを運営してから5年以上経過しましたが、今回はこれまで一度も取り上げたことのない事例について言及します。読者の皆様はご存じかもしれませんが、琉球・沖縄の歴史的大事件である “慶長の役(薩摩の琉球侵攻)” と “沖縄戦” について専門記事はおろか関係資料も配信したことはありません。
菅義偉氏の凄さをまとめてみた
既にご存じかと思われますが、菅義偉首相は、3日の自民党臨時役員会で党総裁選への不出馬を表明し、9月末の(自民党)総裁任期いっぱいで首相を退任する見通しになりました。
参考までに経緯を説明すると、令和2年8月28日、安倍晋三内閣総理大臣・自民党総裁(当時)の辞任表明に伴い、自民党総裁選に立候補・勝利した菅氏が新総裁に就任し、前任者の任期(令和03年9月末)を引き継ぎます。
【私見】コザはなぜこんなに人を引きつけるのか(人が集まるとは言っていない)
先月31日付琉球新報デジタル版に “桐谷健太もハマった コザはなぜこんなに人を引きつけるのか〈映画「ミラクルシティコザ」への道〉1” と題した興味深い記事が掲載されていました。1970年代のコザを舞台にした映画が令和04年1月に県内で先行公開されるに伴う宣伝記事ではありますが、今回はブログ主なりにコザの魅力について言及します。
ちなみに当運営ブログでも沖縄市中央をはじめコザ関連の記事は多数配信しています。ブログ主の地元である宜野湾によりも多くの記事をアップしているのはちょっと笑えますが、それだけ(記事として)取り扱いやすい地区であることは間違いありません。ちなみに取り扱いやすい最大の理由は、現在の沖縄市中央が(規模は違いますが)ローマと同じく、
【備忘録】琉球新報の堕落を象徴する社説
先月23日から今月8日まで開催された東京五輪は、ご存じの通り無事閉幕し、現在は24日からパラリンピックが絶賛開催中です。コロナ禍でコンディション調整が難しい中、アスリートのみなさんの奮闘には頭が下がるブログ主ですが、五輪開催によって社会にまん延した “不公平感” に乗じた琉球新報の社説には嫌な思いを抱いたので、試しに全文を書き写してみました。